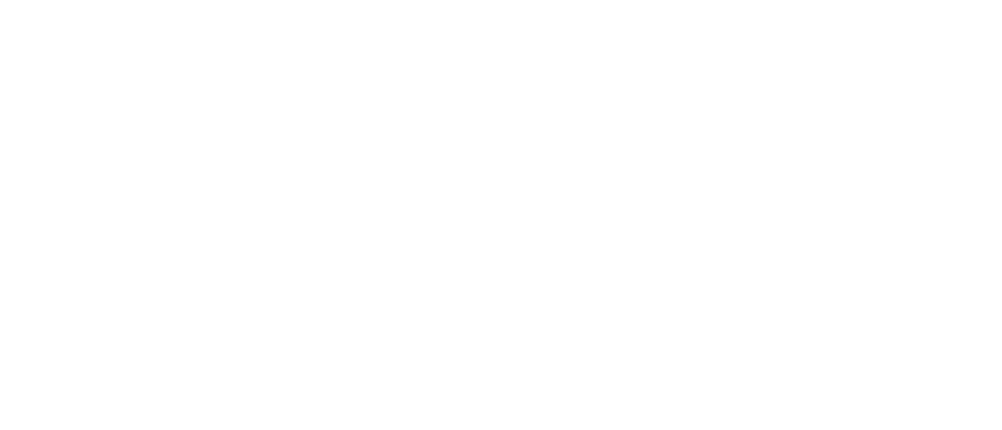ごあいさつ
1983年1月に開業し40年以上経ちました。
約20年前に中国漢方医師との出会いから、中国漢方を学ぶ機会を得ました。
その後、全身的に診察して病気の原因、体質を見極め、各々の患者様に応じた治療を行う事が出来るようになりました。
当院では、漢方治療、鍼治療(全身)などの東洋医学的治療を積極的に取り入れてます。
そして近年注目されている波動治療法の波動治療器を数台導入しております。
波動治療の一つである音叉(おんさ)療法も取り入れました。
最初は私自身、半信半疑で取り入れた音叉療法でしたが、研究と創意工夫を重ねました。
延べ人数にして約3000人の患者様に施し、治療としての手応えを実感致しました。
コロナ関連の疾患にも良い結果が出ております。
医療の一貫としての当院の「メディカル音叉療法」は、より良い治療を求めて現在も研究中です。
特許庁からは、医業、医療情報の提供、代替医療による治療、遠隔医療、美容などの許可をいただいております。
色々な治療法の組み合わせで、更に相乗効果が出ています。
患者様に身体的不安を与えない治療を心がけております。
耳鼻咽喉科疾患に限定せず、御予約、ご相談下さい。